- 障害者雇用で正社員が難しい理由は?
- 正社員登用の実態を知りたい!
- 仕事がない状態から抜け出すには?
「障害者雇用で仕事が見つからない…」
そんなふうに感じて、焦ったり、自信をなくしていませんか?
応募しても落ちる、就職できても「やることがない」そんな経験が続くと、「自分にはもう働ける場所がないのかな…」と思ってしまいますよね。
でも大丈夫。
この記事では、そんな悩みを解決するための「3つの具体策」と「チェックリスト」をご紹介します。
この方法を実践すれば、自分に合った働き方や職場の見つけ方がわかり、迷いから抜け出せるようになりますよ。
実際に、私自身もこの方法で「働けないかも」と悩んでいた時期を乗り越え、今では安心して働ける職場に出会えました。
記事の前半では、仕事が見つからない理由とその整理方法を。
後半では、自分らしい仕事を見つけるための行動ステップを解説します。
 ウキタ
ウキタぜひチェックリストを活用しながら、じっくり読み進めてみてください!


- 名前:ウキタ
- 障害者雇用枠で7年勤務
- 3社で障害者雇用枠勤務
- atGPとdodaャレンジ利用経験
- 人事担当経験あり
障害者雇用で仕事が見つからない5つの原因
障害者雇用で「なかなか仕事が決まらない…」と悩む背景には、いくつかの共通した要因があります。
ここでは代表的な5つを解説していきますね。
- 求人数に偏りがある
- 企業側の受け入れ体制が整っていない
- 自分の条件や希望が高すぎる
- 就労経験・スキル不足
- 過去の離職歴・短期就労による印象ダウン
求人数に偏りがある
障害者雇用における求人は、地域や職種にかなり偏りがあります。
都市部には求人が集中している一方で、地方では選択肢が極端に少ないのが現状。
また、事務や軽作業といった一部の職種に集中しており、他の職種はほとんど募集がないことも多いです。
仮に住んでいる地域に求人があっても、通勤距離や時間、体調とのバランスが合わず断念するケースも少なくありません。
こうした求人の偏りが「仕事が見つからない」状態を生み出してしまいます。
選択肢の幅を広げるためにも、リモート勤務可能な求人や在宅ワーク、通勤に配慮された働き方を提案してくれる支援機関などを積極的に活用することが大切です。
企業側の受け入れ体制が整っていない
企業が障害者を雇用する義務はあるものの、現場での受け入れ体制が整っていないケースは多く見られます。
たとえば、配慮が必要な点が現場の担当者に正しく共有されていなかったり、仕事の切り出しがうまくできておらず「やることがない」状態になったりすることがあります。
表向きは雇用されていても、実際には放置されてしまい社内ニート化で悩む人も少なくありません。
これは、障害の理解不足やコミュニケーション不足が原因になることが多いです。



働きやすさは「制度」だけでなく「現場の理解」も重要ですよ!
自分の条件や希望が高すぎる
「通勤は片道30分以内がいい」「座ってできる仕事がいい」「在宅がいい」など、自分の体調や生活に合った条件を持つことは大事。
ただ希望が多すぎると求人の選択肢が極端に狭まってしまうことがあります。
特に初めての就職やブランク明けの場合、「まずは短時間から始める」「一部条件を妥協して経験を積む」という柔軟さがあると、結果的に自信や実績につながりやすいです。



全ての条件が揃う仕事を一発で探すのではなく、「少しずつ理想に近づける」という考え方が大事!
就労経験・スキル不足
過去に長く働いた経験が少なかったり、職歴が空いていたりすると、求人に応募してもなかなか通過できないことがあります。
企業側は「業務がこなせるか」「継続して働けるか」を重視するため、スキルや実績のある応募者と比較されてしまうのです。
ただし、これは逆に言えば「少しずつ経験を積めば通過率も上がる」ということ。



焦らず、自分のペースで経験を積み上げていくことが大切です。
過去の離職歴・短期就労による印象ダウン
何度も仕事を辞めていたり、短期間で離職を繰り返していると、採用担当者に「またすぐ辞めるのでは?」という印象を持たれてしまうことがあります。
しかし、これには体調の波や配慮不足の職場など、本人に非があるわけではない場合も多いはずです。
面接では正直に過去の経験とその反省、今後の対策を伝えることで、誠実さや前向きな姿勢が評価されることもあります。



もしブランク期間があるなら、
就労移行支援やアルバイト等働ける実績つくりも大切です!
雇用され仕事を与えられない状況から抜け出す方法
障害者雇用で就職できたのに「やることがない」「放置されている」と感じたことはありませんか?
ここではその状況から抜け出すための具体的な方法を5つご紹介します。
- 自分の強み整理
- 受け身状態から脱却
- 上司と密に連絡を取る
- ジョブコーチ制度等利用
自分の強み整理
まず、自分の「できること」をはっきりと言語化することが大切です。
企業側が仕事を任せづらいと感じるのは、応募者のスキルや特性がわからないときによく起こります。
- officeソフトなら基本的な操作をマスターしてる
- 丁寧に確認してミスなく業務ができる
- 軽作業で立ち仕事が可能
どんなに小さなことでもリスト化してみましょう。
また、整理された情報は就労支援スタッフや職場担当者との面談でも活用でき、業務の提案や調整のきっかけになりますよ。
受け身状態から脱却
「指示を待つだけ」の姿勢では、どうしても職場での存在感が薄れてしまいます。
特に障害者枠での就労では、企業側が“何を任せていいかわからない”というケースも多いです。
受け身のままだと「仕事を与えられない」状況に陥りがちです。
たとえば「この資料の整理、お手伝いできますか?」と自分から声をかけるだけでも、印象は大きく変わります。



無理にアピールする必要はありませんが、自分なりにできそうなことを見つけて提案していきましょう!
上司と密に連絡を取る
こまめに上司や担当者とコミュニケーションを取ることで、自分の状況や気持ちをきちんと伝えられるようになります。
仕事を任されない背景には、職場側が「体調に配慮して控えている」こともあれば、「どこまで任せてよいかわからない」という戸惑いもあります。
業務の指示がないと感じたときは、「今、自分ができることを知ってほしい」と伝えたり、「次にやることを確認したい」と声をかけたりするだけで、関係性が前向きになります。



自分の状況を言葉にして共有することで、少しずつ仕事の幅が広がっていきますよ。
ジョブコーチ制度等利用
職場での人間関係や業務の悩みを一人で抱え込まないためにも、「ジョブコーチ制度」などの支援を活用するのはとても効果的です。
ジョブコーチとは、職場に定期的に訪問して、本人と企業側の間をサポートしてくれる専門スタッフのことです。
仕事内容の調整だけでなく、コミュニケーションの橋渡しや定着支援などもしてくれます。



もし「言いたいことがうまく伝えられない」「働きづらさを相談しづらい」と感じているなら、早めに支援機関に相談しましょう!
障害者雇用で“あなたに合う会社”を見つける6つのコツ
「採用されたけど合わなかった」「またすぐ辞めてしまった」…そんな経験を減らすためには、就職前の“会社選び”がとても重要です。ここでは失敗しにくい企業選びのコツを紹介します。
- 働く目的を決める
- 障害特性を理解する
- 自分と同じ障害の方がいる会社を狙う
- 配慮の体制が整ってるか確認
- 口コミサイトを確認する
- 面接後に職場見学を提案する
働く目的を決める
就職活動を始める前に、「なぜ働きたいのか?」を自分の中で明確にしておくと、会社選びの軸がブレにくくなります。たとえば「収入を得て生活を安定させたい」「社会とつながっていたい」「将来の自立に向けたステップにしたい」など、人によって目的はさまざまです。
目的がはっきりすると、「時給が高い仕事」より「無理せず続けられる職場」のほうが自分に合っていると気づくこともあります。



迷ったときは、ノートに書き出すだけでも自分の考えが整理できますよ。
障害特性を理解する
自分の障害特性を正しく理解しておくことは、職場選びの土台になります。
たとえば「長時間立ちっぱなしは難しい」「大きな音や雑多な環境が苦手」「作業手順を明確にしてもらえると安心」など、どんな配慮が必要かを把握しておくと、応募先が本当に自分に合っているかを判断しやすくなります。
また、就職後に「実はできないことが多かった」とギャップに悩まされるリスクも減らせます。



就労支援機関や主治医の協力を得ながら、事前に自分の特性を客観的に整理しておくと安心です。
自分と同じ障害の方がいる会社を狙う
すでに自分と同じ障害を持った社員が働いている会社は、受け入れ体制が整っている可能性が高いです。
たとえば、精神障害を持つ社員が複数在籍していたり、聴覚や視覚に配慮された環境がある会社なら、自分も安心して働ける可能性がぐんと高まります。
求人情報や就労移行支援事業所のスタッフに相談すると、過去に誰がその会社で働いていたかを聞ける場合もあります。



自分だけが“初めてのケース”ではないという事実は、安心感にもつながりますよ!
配慮の体制が整ってるか確認
応募前や面接の段階で、その企業がどのような配慮を行っているかを確認しておくことがとても大事です。
「通院のための遅刻や早退に理解があるか」「業務の切り分けやマニュアルがあるか」「定期的な面談や相談窓口があるか」など、自分が働く上で必要になるサポートがそろっているかどうかは、長く働けるかに直結します。



求人票には書かれていないことも多いので、面接で聞いたり、エージェントや支援機関経由で確認するのがおすすめです。
口コミサイトを確認する
企業の障害者雇用の実態を知るためには、転職口コミサイトなどで実際に働いた人の声を参考にするのも一つの方法です。
「支援制度はあるが形だけだった」「上司の理解があり働きやすかった」など、生の声からは求人票では見えない現場のリアルが見えてきます。
ただし、口コミは個人の感想であり偏りもあるため、鵜呑みにせず“傾向をつかむ”ための材料として活用するのがポイントです。



複数の情報源を比較する視点も忘れずに持ちましょう。
面接後に職場見学を提案する
書類や面接だけではわからない部分を知るには、実際に職場を見学させてもらうのが効果的です。
たとえば「職場の雰囲気が落ち着いているか」「自分にとって刺激が強くないか」「社員の表情や対応に温かみがあるか」などは、現場に行ってみないとわからないものです。
面接の最後に「可能であれば職場の様子を少し見せていただけますか?」と一言添えるだけでも印象は悪くなりません。



自分に合う職場かどうかを肌で感じられる貴重な機会になります。
障害者雇用の仕事探しに役立つマッチ度チェックリスト
就職活動では「この会社で働けそうかどうか」を判断する材料が少なく、なんとなくの印象で応募してしまうこともあるかもしれません。
でも、長く働ける職場を見つけるには、いくつかの視点で客観的にマッチ度をチェックすることが大切です。
たとえば「自分の障害特性が理解されそうか」「業務内容は無理なくできそうか」「職場の雰囲気は安心できそうか」など、あらかじめポイントを整理しておくと、応募後や面接時の違和感を減らすことができます。
| カテゴリ | チェック項目(1行要約) | チェック欄(◯ / △ / ×) |
|---|---|---|
| 自己理解 | 自分の障害特性を把握してる | |
| 自己理解 | 得意・不得意が説明できる | |
| 自己理解 | 働く目的が明確である | |
| 企業制度 | 障害者雇用の実績がある | |
| 企業制度 | 正社員登用の可能性がある | |
| 企業制度 | 勤務条件が自分に合っている | |
| 企業制度 | 給与と福利厚生が生活を支えられる | |
| 企業制度 | 有給取得の配慮がある | |
| 業務内容 | 業務内容が明確に示されている | |
| 業務内容 | 雑務以外のやりがいがある | |
| 業務内容 | 業務調整が可能 | |
| 業務内容 | 作業ペースに無理がない | |
| 職場環境 | 職場の雰囲気が穏やかで安心感ある | |
| 職場環境 | 上司や同僚に相談しやすい | |
| 職場環境 | トラブル時の相談先がある | |
| 職場環境 | ハラスメント対策がある | |
| 配慮体制 | 必要な配慮を相談できる環境 | |
| 配慮体制 | 体調悪化時の対応が決まっている | |
| 配慮体制 | ジョブコーチなどが使える | |
| 配慮体制 | 負担をかけられないよう配慮がある | |
| 将来性 | スキルアップや評価制度がある | |
| 将来性 | 離職率が低く定着しやすい | |
| 将来性 | 通勤しやすい環境 | |
| 将来性 | キャリア相談ができる | |
| 最終判断 | この職場で働く姿を想像できる | |
| 最終判断 | この会社で長く続けらると感じる |
- 点数方式を使う場合:「◯=2点、△=1点、×=0点」で採点可能。
- 合計40点以上なら、かなりマッチ度が高いと判断できます。
- 面接・見学後や家族・支援者と一緒に確認するのもおすすめです。
必見!自分にあった仕事探しのやり方3選
「仕事を探したいけど、どこから始めたらいいか分からない…」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは障害者雇用での就職を目指す方におすすめの3つの方法をご紹介します。
- 障害者雇用専門のエージェントに登録する
- 就労移行支援の見学を予約する
- ハローワークに行く
障害者雇用専門のエージェントに登録する
障害者雇用に特化した転職エージェントは、求人紹介だけでなく、面接対策や企業との調整など幅広いサポートをしてくれます。
たとえば「atGP」や「dodaチャレンジ」などは、障害に理解のある企業と多くのつながりがあり、配慮内容や働きやすさの情報も事前に確認できます。
また、キャリアアドバイザーがついて相談に乗ってくれるので、ひとりで就職活動を進める不安も軽減されます。
エージェントを活用すれば、自分の状況や希望に合った職場を効率よく探すことができます。
就労移行支援の見学を予約する
就労移行支援は、障害がある方が「働く力」を身につけるための通所型の支援サービスです。事務作業や軽作業の訓練だけでなく、ビジネスマナーや面接練習、就活スケジュールの管理など、実践的なサポートを受けられます。
多くの事業所では、見学や体験利用が可能です。
「いきなり働くのは不安」「まずはリズムを整えたい」という方にも向いています。
どの事業所も特色が異なるので、気になる場所があればまずは見学を申し込んで、雰囲気を確かめてみましょう。
ハローワークに行く
障害者雇用の就職活動でも、ハローワークは強い味方になります。
各地に「障害者専門の窓口」があり、障害の特性や配慮事項をふまえて求人紹介をしてくれるほか、面接対策や履歴書の添削も受けられます。
特に「障害者トライアル雇用」などの制度は、実際に働きながら職場との相性を確かめられる点で安心です。



職員さんと話しながら、無理のないペースで仕事を探していけるので、「久しぶりの就活で不安…」という方にもおすすめ!
障害者雇用もう無理かもと思ったときに読んでほしいこと
何度も不採用になったり、職場に馴染めなかったりすると、「もう働くのは無理かもしれない」と感じることがあると思います。
そんなとき、思い出してほしい考え方を3つお伝えしますね。
- 「働けない=自分に価値がない」わけじゃない
- 自分の強みを知り、希望を少しずつ可視化する
- 一人で抱えず“共感してくれる人”とつながる
「働けない=自分に価値がない」わけじゃない
うまくいかない状況が続くと、「働けない自分はダメなんだ」と思い込んでしまいがちです。
でも、働けないことと人としての価値はまったく別物。
体調や環境によって、今はたまたま働けないだけというケースもあります。
実際に、数ヶ月〜数年の準備期間を経て安定して働けるようになった方もたくさんいますよ。
自分を否定せず、まずは「疲れたなら休んでいい」「少しずつで大丈夫」と思ってみてください。



心と体が回復すれば、動けるタイミングは必ず来ます。
自分の才能を知り、希望を少しずつ可視化する
「どうせ自分には何もできない」と思っていると、動く気力も湧きません。
でも、才能は必ず誰にでもあります。それが目立つスキルじゃなくても、「人の話をしっかり聞ける」「ルールを守るのが得意」「黙々と作業できる」など、職場で活きる特性はたくさんあるんです。
ノートに「できること」を3つ書くだけでも、少し前向きになれます。
小さな強みに気づけたら、次は「どんな職場が合いそうか」など希望を書き出してみましょう。
気持ちの整理にもつながります。
一人で抱えず“共感してくれる人”とつながる
辛さをひとりで抱えてしまうと、どんどん視野が狭くなってしまいます。
「自分だけがうまくいってない」と感じると、気持ちが余計につらくなりますよね?
でも、実は同じように悩んでいる人はたくさんいます。
就労移行支援のスタッフ、SNS上の当事者コミュニティ、ピアサポート(同じ経験を持つ人の支援)など、共感してくれる人は必ずいます。
「わかるよ」と言ってもらえるだけで、心がふっと軽くなることもあります。



誰かとつながることで、回復のきっかけをつかめることもあるんです。
障害者雇用に関するよくあるQ&Aまとめ
- 障害者雇用でいるだけ(社にニート)状態になるのはなぜ?
-
障害者雇用では、法定雇用率の達成が企業の目的となりやすく、業務内容が限定されることで成長機会が乏しく「いるだけ」の状態になることがあります。
- 障害者が仕事を見つけるために何を最初に始めればいいの?
-
障害者が仕事を見つけるために最初に始めるべきことは、自己理解を深めることです。
自分の障害特性や配慮が必要な点、得意・不得意を整理し、どのような働き方が合っているかを明確にしましょう。
そのうえで、ハローワークや就労移行支援、障害者向け転職サイトなどの支援機関を活用して情報収集を行い、自分に合った仕事探しを進めるのが効果的です。
- 自分の適性を見極めるためにどうすればいいの?
-
自分の適性を見極めるには、まず過去の経験を振り返り、得意だった作業や苦手だった環境を整理することが大切です。
次に、職業適性検査や就労移行支援事業所などの支援機関を活用し、専門的な視点からのアドバイスを受けましょう。
実習や体験を通じて実際の業務に触れることも、適性を知るうえで有効です。
- 就労移行支援を受けることで何が変わるの?
-
就労移行支援を受けることで、働くために必要なスキルや生活リズムが整い、自信を持って就職活動に取り組めるようになります。
履歴書の書き方や面接練習、職場実習など実践的な支援を受けられ、自分に合った職場を見つけやすくなります。
また、就職後も定着支援があるため、長く働き続ける土台が築けますよ。
【まとめ】仕事が見つからないのは、あなたのせいじゃない
障害者雇用で仕事が見つからないと感じることは、決して珍しいことではありません。
求人の数が少なかったり、企業側の理解が不十分だったり、そもそも働ける条件に合う職場がなかなか見つからない。
そんな“仕組みの問題”が、あなたを悩ませているだけかもしれません。
でも、それは「あなたが悪い」からではありません。
むしろ、何度も落ちても、諦めずに検索し、この記事にたどり着いたあなたは、もう十分に頑張っています。
本記事で紹介した「3つの行動」や「マッチ度チェックリスト」、「自分に合う会社の見つけ方」を少しずつ試してみてください。
今すぐ完璧にやる必要はありません。
ゆっくりでも、確実に、次の一歩に近づいていけるはずです。



あなたがあなたらしく働ける場所は、きっとあります。
どうか、自分のペースで歩みを止めずにいてください。
仕事が見つからないと悩んでるあなたへ
あなたに合う職場を見つけるには、「求人を見る前に、相談できる人がいる」ことがとても大切です。
サポートの手厚さ・求人の多さ・希望条件のマッチ度など、自分に合ったサービスを選んでみてください。
- アットジーピー【atGP】:スカウト機能つきで在職中でも安心
- dodaチャレンジ:あなた専任のアドバイザーが親身に対応
- 【ランスタッド】:大手・外資企業の障害者求人に強い

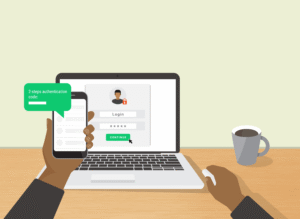







コメント