- 障害者枠って応募してもなかなか通らない…
- 書類選考すら突破できなくて、自信がなくなってきた
こんな風に感じたこことありませんか?
障害者雇用は“狭き門”とよく言われますが、実際その理由がはっきりわからずに悩んでいる方も多いです。
でも安心してください。
本記事では、障害者雇用でなぜ採用されにくいのかという根本原因と、それをどう乗り越えるかをわかりやすく解説!
この記事で紹介する「採用されやすい人の共通点」や「障害者雇用の選考を突破するための3ステップ」を実践すれば、今まで書類や面接でつまずいていた方でも、確実に選考通過率が上がるはずです!
 ウキタ
ウキタ実際に僕もこの方法を実践して、50社以上落ち続けた状態でしたが無事内定ゲット!
記事の前半では、「障害者雇用が狭き門になる理由」や「落ちる人に共通するポイント」を解説。
後半では、「採用される人の特徴」「面接・書類対策のコツ」「おすすめの支援機関」について具体的に紹介していきます。


- 名前:ウキタ
- 障害者雇用枠で7年勤務
- 3社で障害者雇用枠勤務
- atGPとdodaャレンジ利用経験
- 人事担当経験あり
障害者雇用が狭き門とされる7つの理由
「障害者枠って、なんでこんなに受かりにくいの?」って感じたことないですか?
実は、そう思ってる人めちゃくちゃ多いんです。
ここでは、なぜ“狭き門”って言われてしまうのか、その主な7つの理由をわかりやすくお話ししていきます。
法定雇用率の達成状況と求人の実態
障害者を雇う割合、2025年7月からは「2.7%以上」が義務になりました。
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
令和2023年度 令和2024年4月 令和8年2025月 民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7% 対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上
つまり、従業員40人以上の会社は障害者を1人以上雇わないとダメってこと。
でも現実は達成してる企業は全体の約50%。半分は守れてないんです。
企業側がまだまだ障害者協に積極的に取り組んでいないとも言えます。



中小企業ほど体制が整ってなくて、求人を出していない会社もまだまだ多いんです・
応募者の増加と採用倍率の上昇
障害者雇用の競争率、年々上がってます。厚生労働省の2023年度データでは、新規求職申込件数が前年度比で6.9%も増加。
一方、就職件数も8.0%増えてるとはいえ、求職者の増え方が大きいから倍率は高止まりなんです。
特に「正社員・事務職・大手企業」みたいな人気条件は、1名枠に対して30人以上が応募することも。
障害者雇用枠では一般雇用では入れない企業でも働けるチャンスがあり、1つの企業に応募殺到する現実があります。逆を言えばあまり知名度の高くない中小企業なら、応募が殺到せずすんなり内定を勝ち取れます。



障害者雇用が狭き門ではなく、「大手大企業」が狭き門だと理解しよう!
求人票に潜む「空求人」「形式的な募集」
「出てるのに受からない求人」って、実は“空求人”かもしれません。
- ハロワ担当者が求人掲載の削除してない
- 応募を締め切った後も、条件に合う応募者を引き続き集めるために掲載を延長
- 掲載料が無料でコストがかからないから
- 広告としての効果(宣伝目的)
上記の理由からハローワークでは空求人多めなんです。



空求人は採用する目的がゼロの場合があるため、
いくら書類選考を送ったとて受からないことがほとんどです。
雇用人数自体が少ない
企業が出す障害者雇用の求人って、基本1名、多くても2〜3名なことがほとんど。
というのも障害者雇用採用は「法定雇用率を満たすための採用」であることがほとんどだから。
1人退職して法定雇用率が不足したから1人採用というやり方なので、1企業で1名採用が基本です。
実際求人情報サイトを見ても、求人の9割以上が「若干名」って書かれてます。



法定雇用率を満たすためだけの“最低限”しか雇わない企業が多いので、狭き門になりやすいです。
障害内容による線引き
どんな障害でもOKって思いたいけど、実際は企業によって対応できる障害の種類に差があります。
たとえばある大手企業では、「身体障害の方のみ採用実績あり」と掲載している例もあります。
また重度障害に分類される障害者の方についてはそもそも応募の段階で不採用になることも・・・。
重度障害の方は採用のハードルが低い特例子会社を目指すのが無難です。



障害で採用の合否が決まるのは納得いきませんが、
現実は少し厳しいのが実情ですね。
ブランク期間(空白期間)が長い
ブランクがあるだけで即NGではありません。
ただし、その期間の過ごし方や理由を聞かれたとき、ちゃんと説明できないと「働く意欲が低いのかな?」と見られることも。
たとえば、
- AIを使いこなすため○○スクールで学習していた
- 2年間は療養していた
- 就労移行支援に通って訓練していた
など、前向きな説明があると印象は変わります。



僕は6か月以上のブランク期間がありましたが、
「ホームページ作成スキルを磨いていた」という理由でOKでした。
年齢による難しさ
建前では「年齢制限なし」がルールですが、実際の現場では年齢が上がるほどハードルも上がる傾向があります。
特に40代以上になると、「若手の方が育成しやすい」「定年が近い」と判断されてしまうことも。
実際にハローワーク求人でも「64歳以下(定年65歳)」のような記載が残っていたりします。



年齢が高くなるほど、職歴やスキルの“説得力”がより重要です!
必見!障害者雇用で不採用になる4つの理由
障害者雇用に応募しても「なかなか採用されない」と感じる方は多いのではないでしょうか。なぜなら、選考の段階ごとに不採用になりやすいポイントがあるからです。
- 書類選考で不採用
- 面接で不採用
- 実習や試用期間で不採用
- 障害の内容で不採用
例えば、書類選考では経験や志望動機が十分に伝わらないケースがあります。
面接では、自分の強みや配慮してほしい点をうまく説明できず評価が下がることも。
さらに、実習や試用期間では仕事のペースや職場環境に適応できないと判断されることが少なくありません。
障害の内容や特性が仕事内容と合わない場合も影響します。



不採用の理由を理解して対策することが、採用への第一歩になるのです。


採用されやすい人の特徴10選
「じゃあ逆に、受かってる人ってどんな人なの?」と気になりますよね。実は、企業から選ばれている人たちには共通点があります!
- 素直な人
- できることを理解
- 安定して働ける
- コミュニケーションが取れる
- 協調性がある
- 意欲がある
- 基本的なマナーが身についている
- サポートを活用できる
- コツコツ取り組める
- 職場に順応できる
例えば、素直にアドバイスを受け入れたり、自分の強みと弱みを理解している人は成長が早い傾向があります。
さらに、安定して出勤できることや、挨拶や時間を守るなど基本的なマナーも重要です。
具体的には、協調性を持ってチームに合わせられる、困った時にサポートを活用できる、コツコツ作業を継続できるといった点が評価されます。



まとめると意欲や職場に適応できる人は採用されやすいのです。


障害者雇用の選考を突破するための3ステップ
「どうしたら受かるの?」という一番の疑問に、ここでは具体的に答えていきます。
やみくもに応募するんじゃなく、選考通過する人がやっている3つのステップを押さえておくと、結果がぐっと変わってきますよ。
ひとりでの就職活動に限界を感じたら、まずは障害者向けの転職エージェントに相談してみてください。
たとえば【dodaチャレンジ】や【atGP】は、障害の特性や配慮希望に合った求人を提案してくれるだけではありません。企業との間に入って条件の調整もしてくれます。



職場の雰囲気や配属先の実情まで聞けることもあるので入社後のミスマッチも防げます。
履歴書や職務経歴書は、ただ書くだけじゃダメ。ちゃんと“伝わるか”がポイントです。
- 配慮してほしい内容は書かれているか
- 志望動機に熱意があるか
- 職歴のブランクは説明されているか
など、誰か第三者に見てもらうのがオススメです。
支援機関やエージェントに添削してもらえば、見た目の印象もガラッと変わります。



正直、自分で調べるよりプロのアドバイスが早くて的確です!
「なんとかなるでしょ」と面接に挑むのはNG。聞かれることはだいたい決まってるので、準備すれば確実に対応できます。



僕もなんとかなる派でしたがいざ面接をすると何も話せなくなって、
「早く時間よ進め!」と心で唱える嫌な経験をしました(笑)
就労支援やエージェントでは模擬面接もしてくれるので、練習しておくと本番で落ち着いて話せます。
障害種別!就職難易度と成功のヒント
実は、障害者雇用といっても、障害の種類によって企業の受け入れ体制や就職のしやすさが少しずつ違います。
ここでは「身体・精神・知的」の3つに分けて、就職の難易度や成功のコツをお伝えします!
身体障害のある人が選ばれる職種と対策
身体障害のある方は、障害者雇用の中では比較的採用されやすい傾向があります。
理由は、企業が対応しやすいケース(例:下肢障害の方へのバリアフリー設備など)が多いためです。
事務職や軽作業、データ入力など、座ってできる業務は特に人気。
ライバルも多いので、志望動機や自己PRで「職務への理解」や「配慮の希望」を具体的に伝えるのが大事です。
精神障害のある人が抱える課題と突破法
精神障害のある方は、職場での配慮やコミュニケーションの難しさがネックになることがあります。
ただ、最近はハローワークやエージェント側が「精神障害者の積極的なプッシュ」もあり、内定数は身体障碍者よりも増加傾向です。
ポイントは、症状の安定と自己理解。無理なく働ける時間や仕事内容を見極めて、支援機関のサポートを受けながら活動するのが成功への近道です。
知的障害のある人に必要な支援とマッチングのコツ
知的障害のある方は、業務内容の理解や指示の受け取り方に工夫が必要になるため、企業側にしっかり支援体制があるかどうかがポイントになります。
例えば、仕事内容がルーチン化されている軽作業や清掃、パッキングなどの業務はマッチしやすいです。



支援学校や就労支援機関と連携して、サポート体制が整ってる企業で働くのが大事!
障害者雇用に関するよくある疑問
- 障害者雇用枠は何社で受かるか?
-
障害者雇用枠で何社受ければ受かるかは人によって異なりますが、一般的には10〜30社程度応募してようやく1社通過するケースが多いです。
特に人気の職種や大手企業は倍率が高く、書類で落ちることも珍しくありません。
受かるまでに数十社以上受ける人も少なくないので、焦らず、支援機関やエージェントを活用しながら進めるのがおすすめです。
- 障害者雇用枠で受かる確率はどれくらいですか?
-
障害者雇用枠での採用確率は、応募全体の平均で10~30%程度と言われています。
つまり、10社応募して1~3社通れば良い方です。
職種や企業規模、障害の内容によっても差がありますが、特に人気の事務職や正社員枠は競争が激しくなりがちです。
採用率を上げるには、自己理解・書類の質・面接対策がカギになります。
まとめ障害者雇用でも対策すれば突破可能!
「障害者雇用は狭き門」って言われるけど、それってただの現実の一面にすぎません。
たしかに倍率は高いし、求人は少ないかもしれません。
でも、“なぜ通らないのか”を知って、“どうしたら通るのか”を対策すれば、状況は変えられます。
この流れを意識するだけで、採用に近づく確率はグッと上がります。
そして、ひとりで頑張りすぎなくて大丈夫です。
支援機関や転職エージェントなど、あなたをサポートしてくれる人たちはたくさんいます。



上手に頼りながら、あなたにぴったりの働き方を見つけていきましょう。
この記事が、あなたの「もう一度頑張ってみよう」のきっかけになったら嬉しいです。応援しています!
なかなか障害者雇用で内定がもらえないあなたへ
「なぜか書類が通らない」「どんな求人が合ってるのかわからない」——
そんなときこそ、障害者支援に特化したエージェントに頼るのが近道です。
▶ 内定がもらえない状況をプロと一緒に解消!
- ✅【ランスタッド】(障害者支援):外資・大手企業の障害者求人に強い
- ✅ アットジーピー【atGP】:スカウト機能付きで在籍しながら転職活動できる!
- ✅ dodaチャレンジ:専任アドバイザーによるキャリア提案が強み

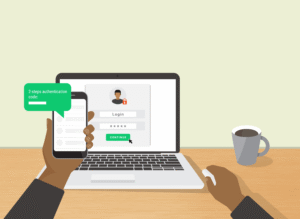






コメント