「障害者雇用って年齢制限ある?この年齢でも応募していい?」そんなモヤモヤありますよね?
40〜60代でブランクがあると、求人の「年齢不問」を信じていいのか不安…。
大丈夫。この記事はその悩みを事実と具体策で解決します。
本記事で紹介する「年齢の壁を越える応募戦略と求人の見極め方」を実践すれば、初心者でも採用に近づけます!
前半では「障害者雇用年齢制限は何歳まで?」の法律と現実、年代・障害別の状況を整理。後半では採用されやすい職種、効率的な探し方、年代別のコツとFAQを解説します。
 ウキタ
ウキタ現在就職活動で不安なあなたはぜひ最後までご覧ください!


- 名前:ウキタ
- 障害者雇用枠で7年勤務
- 3社で障害者雇用枠勤務
- atGPとdodaャレンジ利用経験
- 人事担当経験あり
障害者雇用の年齢制限法律と現状解説
障害者雇用では、法律上は年齢による制限が禁止されていますが、現場の採用実態や企業側の事情によって、年齢が採用に影響することもあります。
ここでは、法律上のルールと実態、そして年齢が上がることで転職が難しくなる背景を解説。
法律上の制限(雇用対策法)と例外ケース
障害者雇用も含め、求人募集での年齢制限は「雇用対策法」により原則禁止されています。
2007年10月の改正で、事業主は年齢にかかわらず均等な採用機会を与える義務が明確化され、「◯歳以下」などの条件は基本的に記載できなくなりました(厚生労働省)。
ただし例外もあり、定年年齢未満の人を対象にする場合や、長期勤続によるキャリア形成を目的とした若年者の募集、特定職務の技能継が必要なケースでは年齢条件が認められます。



法律上は年齢制限なし。ただ一部の職種や条件では年齢が考慮されることもあります。
実態としての年齢ハードル
法律上は年齢制限がないとはいえ、実際には「若手が有利」と感じる場面は少なくありません。
障害者職業総合センターの調査でも、中高年の障害者求職者は若年層より採用が難しい傾向が見られます。
企業側は同じ能力であれば、柔軟性や吸収力の高い若年層を好む傾向があるためです。
ただし、実際の採用データでは40代・50代以上でも採用実績は多数あり、ある調査では中高年求職者の約7割が採用に至っています。
これは法定雇用率の引き上げなどで企業が幅広い年齢層の障害者を受け入れている証拠。



年齢だけで諦める必要はないことを知っておこう!
年齢が上がると転職が難しくなる理由
年齢が上がると転職が難しくなる背景には、体力や健康面の懸念、新しい業務への適応スピード、長期的な雇用期間の見込みなどがあります。
企業は採用後の教育コストや配置計画を考えるため、より若い層を優先しやすいのです。
ただし障害者雇用の場合、法定雇用率を満たす必要があるため、40~50代の採用も一般枠より活発。
特に同じ職種の経験や専門スキルがある中高年は、若手よりも即戦力として評価されることも。



年齢によるハードルはゼロではないものの、障害者雇用では実務経験や勤怠の安定性が評価されます。
障障種目別年齢雇用傾向
障害の種類によって、年齢層の構成や雇用される傾向に違いがあります。
それぞれの障害区分ごとに、どの年代の方が多く働いているか、現状を見てみましょう。
身体障害
身体障害者の雇用において、年齢層には特徴的な傾向があります。
| 年齢階級 | 雇用割合(%) |
|---|---|
| 29歳以下 | 6.5 |
| 30~39歳 | 13.2 |
| 40~49歳 | 18.0 |
| 50~59歳 | 22.8 |
| 60~64歳 | 21.8 |
| 65歳以上 | 17.4 |
理由は、身体障害の方は長期で働ける人が多いため結果として高齢者の割合が高め。
厚生労働省の調査(令和5年6月時点)によると、身体障害者の雇用者のうち、65歳以上が17.4%と最も高い割合を占めています。
逆に、49歳以下の若年層の雇用割合は比較的低い傾向があります。
障害のある方が若いうちに就職の機会を得るのが難しい現状があるのです。



年齢別の雇用状況には偏りが見られ、高齢層に比べて若年層の支援が今後の課題といえるでしょう。
知的障害の年齢層
| 年齢階級 | 雇用割合(%) |
|---|---|
| 19歳以下 | 2.0 |
| 20~24歳 | 25.0 |
| 25~29歳 | 18.1 |
| 30~34歳 | 18.0 |
| 35~39歳 | 9.2 |
| 40~44歳 | 8.0 |
| 45~49歳 | 5.1 |
| 50~54歳 | 8.6 |
| 55~59歳 | 2.6 |
| 60~64歳 | 1.9 |
| 65歳以上 | 0.5 |
知的障害者の雇用においては、若年層の割合が高い点が特徴。
なぜなら、特別支援学校を卒業後、すぐに就労移行支援などを通じて職場に入るケースが多いためです。
厚生労働省の調査(令和5年)では、20~24歳が25.0%と最も多く、30代までの合計で約70%を占めています。
逆に、40代以降になると割合は大きく減少します。
傾向として知的霜害者の定着率が低く、年齢が上がるにつれ再就職が難しくなる現状があるのです。



1社目で手厚いサポート体制がある会社で、
長く働き続けるのが大切ですね!
精神障害
精神障害者の雇用では、中年層と若年層に多い傾向があります。
なぜなら、うつ病や発達障害など働き盛りの年齢で発症するケースが多いためです。
厚生労働省の調査(令和5年)では、最も多いのが50~54歳で15.7%、次いで25~29歳が15.1%、30~34歳が13.4%となっています。
| 年齢階級 | 雇用割合(%) |
|---|---|
| 19歳以下 | 0.3 |
| 20~24歳 | 9.5 |
| 25~29歳 | 15.1 |
| 30~34歳 | 13.4 |
| 35~39歳 | 12.2 |
| 40~44歳 | 12.3 |
| 45~49歳 | 12.1 |
| 50~54歳 | 15.7 |
| 55~59歳 | 5.8 |
| 60~64歳 | 2.6 |
| 65歳以上 | 0.8 |
20代後半から50代前半までの働き盛りが中心です。
一方で、60歳以上になると雇用割合は大きく下がります。



精神障害者の就労支援は特定の年齢層に集中しがちであり、年齢に応じた対応が求められますね。
発達障害
発達障害のある方が多く雇用されているのは、比較的若い年齢層です。
なぜなら、近年では発達障害の早期診断や支援体制が整い、若年層が就労支援につながりやすくなっているためです。厚生労働省による令和5年の調査によると、最も割合が高いのは20~24歳で23.1%、次いで25~29歳が21.4%、30~34歳が16.7%と続いています。
| 年齢階級 | 雇用割合(%) |
|---|---|
| 19歳以下 | 3.7 |
| 20~24歳 | 23.1 |
| 25~29歳 | 21.4 |
| 30~34歳 | 16.7 |
| 35~39歳 | 10.1 |
| 40~44歳 | 7.1 |
| 45~49歳 | 6.5 |
| 50~54歳 | 6.6 |
| 55~59歳 | 2.9 |
| 60~64歳 | 1.4 |
| 65歳以上 | 0.6 |



就職のスタートを迎える世代での雇用が中心となっているのが現状です。
長く働くための4つの戦略
障害者雇用で長く安定して働くためには、雇用形態や制度の活用、働き方の工夫、職場での関係づくりなど、いくつかのポイントがあります。
ここでは、その中でも特に重要な4つの戦略を解説します。
非正規から無期雇用への切り替え方法
契約社員やパートなど有期契約で働く場合、安定就業を目指すなら「無期転換ルール」を活用するのが有効です。
企業側は申込みを断れないため、安定した雇用が確保しやすくなります。



障害者雇用は非正規比率が高いため、この制度を知っているかどうかで将来の安定度は大きく変わります!
60歳・65歳以上の雇用機会確保義務(2024年改正)
「高年齢者雇用安定法」により、企業は65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられています。
具体的には、
- 定年の引き上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年制廃止
いずれかを選択します。
2023年の調査では、99.9%の企業が何らかの措置を実施しており、特に継続雇用制度が約7割と最多。



障害者雇用の場合もこの制度は適用されます!
求人を見る際は定年後の雇用形態や延長制度の有無を必ず確認。
健康・体力に合わせた勤務形態の工夫
長く働くには、自分の体調や障害特性に合わせた働き方を選ぶことが欠かせません。
- 週3〜4日の勤務や短時間シフト
- 在宅勤務の活用
- 午前中だけ勤務
負担を軽減できる選択肢は上記のように複数あります。
無理をして体調を崩すと継続雇用が難しくなるため、最初から希望条件を明確に伝えることが重要です。



健康維持を前提に働くことで、結果的に長期的な就業が可能になります!
職場環境・人間関係の安定化
安定して働き続けるためには、職場環境や人間関係の影響も大きいです。
障害者雇用では、配慮事項やサポート体制が整っているかが重要なポイントになります。
- バリアフリーな物理的環境
- ICT・ツールの活用
- 適切な業務内容と配慮
- 人的サポート体制
- 相談しやすい上司や同僚がいる
- 組織文化・雰囲気
- 成長・自立への支援
- 安全性と健康管理
- 業務内容が明確で指示が一貫
上記の項目から自分が必要とする配慮を考え会社を選ぶのが大事ですね。
また、自分からも適度なコミュニケーションを取ることで、誤解やトラブルを減らせます。



職場見学や体験を通じて雰囲気を確認してから入社することは、長期的な就業の成功につながります。
高年齢でも採用されやすい業種・職種
高年齢の障害者雇用では、体力負担の少なさや経験を活かせることが採用のポイントになります。
ここでは、比較的年齢に関係なくチャンスのある職種を6つ紹介します。
事務職
デスクワークが中心で身体的負担が少なく、幅広い世代で働きやすい職種です。
必要とされるのはExcelやWordなどの基本スキルで、特別な資格がなくても応募可能な場合が多いです。
例えば、書類作成やデータ入力、電話応対などは、経験があれば即戦力として評価されます。
事務職は正確さや丁寧さが重視されるため、年齢よりも仕事の質や安定した勤務態度が採用の決め手になるからです。



要するに、経験を活かしやすく、長く続けやすい職種と言えます。
サービス・接客系
接客や販売など、人と接する機会の多い職種は、高齢者や障害者でも活躍できる場が増えています。
理由は、多様性を重視する企業が増え、年齢や背景に関わらず幅広い人材を受け入れているからです。
具体的には、飲食店のホール業務や小売店のレジ対応、宿泊施設のフロントなどがあります。



人との会話や笑顔での対応が求められますが、経験や人柄が強みになるため、年齢は大きな壁になりにくいですよ!
軽作業・倉庫作業
工場や倉庫でのルーティンワークは、覚えやすく年齢の影響を受けにくい仕事です。
例えば、商品の検品や梱包、ピッキングなど、単純作業が多く、体力的な負担も比較的軽めです。
なぜなら、多くの企業がシフト制や短時間勤務を導入しており、自分の体調や生活リズムに合わせやすいからです。
また、障害者雇用枠でも募集が多く、未経験から挑戦しやすいのも特徴です。
福祉・介護関連職
介護や福祉分野は人手不足が深刻で、高年齢者の採用にも積極的です。
資格が必要な場合もありますが、介護補助や送迎業務など資格不要の仕事も多く存在。
例えば、利用者の生活支援や話し相手になる業務は、人生経験や包容力が活かせます。



利用者や同僚からの信頼関係が仕事の質を高めるため、年齢がむしろプラス評価になるケースが多いからです。
清掃・設備管理
オフィスや商業施設、病院などの清掃・設備管理は、高齢層でも働きやすい分野です。
理由は、ルーティン化された業務が多く、慣れると安定して続けやすいから。
具体的な業務は、床や窓の清掃、ゴミ回収、設備点検などがあります。



短時間勤務や早朝・夜間のシフトなど働き方が選びやすく、定年後も継続できる職種のひとつです。
就労継続支援A型・B型事業所
障害特性や体調に配慮された環境で働けるのが、就労継続支援事業所の強みです
A型は雇用契約を結んで働く形態、B型は契約を結ばず作業分に応じた工賃を受け取る形態です。
例えば、簡単な軽作業や手工芸、農作業などがあり、自分のペースで取り組めます。
事業所は就労支援と生活支援を兼ねており、体調に合わせて働ける環境が整っているからです。



高年齢層にとっても安心して続けられる選択肢ですね。
高年齢の仕事探しの方法【効率的な求人の見つけ方】
高年齢での転職は、限られた体力や時間を無駄にしないためにも、求人の探し方が重要です。
ここでは効率的かつ安心して探せる3つの方法を紹介します。
ハローワークを活用
ハローワークは全国に拠点があり、無料で求人を紹介してくれる公共サービスです。
特に「障害者専門窓口」では、障害特性や体調に配慮した求人を案内してもらえます。
例えば、地元の企業や公共団体の採用情報など、地域密着型の求人が多いのが特徴です。
ただし、求人票の条件が実際と異なる場合もあるため、事前に企業の雰囲気や配慮状況を確認してから応募することが大切です



企業見学や職場実習を活用すれば、入社後のミスマッチを減らせます。
転職エージェントを活用
転職エージェントは、求人紹介だけでなく、応募書類の作成支援や面接対策まで一貫してサポートしてくれます。
なぜなら、企業との間に入り、条件交渉や職場環境の確認も行ってくれるからです。
例えば「ランスタッド」や「dodaチャレンジ」は、障害者雇用に特化し、大手企業や優良企業の求人も多く取り扱っています。
非公開求人や正社員登用実績がある案件もあり、年齢や障害特性に合った仕事が見つかりやすいです。
効率的に探すなら複数登録が有効です。
就労支援事業所の活用(訓練・職場体験)
就労支援事業所は、障害のある方がスムーズに職場へ移行できるよう、職業訓練や職場体験の機会を提供します。
具体的には、パソコンスキル習得、軽作業の訓練、模擬職場での実習などを通して、自信をつけながら就職活動に臨めます。



職場定着支援も受けられるため、入社後の不安軽減にもつながりますよ。
長く働くための準備段階として非常に有効な選択肢です。
高年齢層の転職成功ポイント【年代別戦略】
年齢ごとに強みや課題が異なるため、転職戦略も変える必要があります。
ここでは40代〜60代までの年代別のポイントについて解説します!
40代の戦略(即戦力スキル+安定感)
40代は、経験の豊富さと柔軟な働き方の両立が武器になります。
なぜなら、企業はこの世代に即戦力としてのスキルや業務知識を求めつつ、長期的な貢献も期待しているから。
例えば、事務や軽作業では業務効率化の工夫を提案できること、福祉職では利用者や同僚との円滑な連携ができることが評価されます。



安定した勤怠とコミュニケーション力をアピールし、支援機関や転職エージェントを活用して希望条件に合う求人を探すことが成功の近道です。
50代の戦略(経験+勤怠の安定性)
50代は、これまでの職務経験に加えて「信頼できる勤務の安定性」が強みになります。
理由は、企業が求めるのは即戦力と同時に、安定した勤務が続けられる人材だからです。
例えば、製造業での熟練作業や、清掃・設備管理での安全管理の意識は高く評価されます。
また、応募時には健康状態の自己管理方法や、過去の安定勤務の実績を具体的に伝えると説得力が増します。



短時間勤務や週3〜4日勤務などの条件をうまく交渉すれば、長期雇用の可能性が高まりますよ。
60代の戦略(健康配慮+短時間勤務)
60代では、健康面の配慮と無理のない勤務形態が重要です。
体力や通勤負担が採用の可否に直結しやすいためです。
例えば、午前中のみの事務補助や、近隣での軽作業、週2〜3日の勤務など、柔軟な働き方を提示できると採用されやすくなります。
さらに、これまでの経験を活かせる職種を選び、体調管理や定期通院の計画を事前に説明しておくと企業の安心感が高まります。



健康維持と無理のない勤務ペースを両立させることがカギ!
障害者雇用年齢制限に関するよくある質問
- H3 50代・60代でも本当に採用される?
-
50代・60代でも、障害者雇用枠で採用される実例があります。
例えば、転職支援サービス「dodaチャレンジ」では、50代男性が上肢・下肢障害を抱えながら事務職で採用され、社員からの信頼を得て活躍している事例があります。
また、50代の腎臓機能障害の方が総務職として週2日勤務で採用され、長く働いている実例も紹介されています
- 年齢不問求人は信頼できる?
-
「年齢不問」と明記された障害者雇用求人は、実際に幅広い年代の応募を受け入れる意図があるケースが多いです。
ただし実際の採用は、経験や適性、就業条件の合致度に左右されます。
信頼性を確認するには、企業の採用実績や支援機関の紹介求人かどうかをチェックすると安心です。
- 障害者雇用の対象となる障害の種類は?
-
障害者雇用の対象は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病等と幅広いです。
- 身体障害:視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)
- 知的障害:知的機能に制限があり、生活や就労に配慮が必要な場合
- 精神障害:うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害など
- 発達障害:自閉症スペクトラム、ADHD、学習障害など
- 難病等:厚生労働省が定める指定難病で就労配慮が必要な場合
いずれも「障害者手帳」で対象となり、雇用義務や支援制度の適用が受けられます。
記事のまとめ
障害者雇用における高年齢での就職・転職は、法律上の年齢制限こそないものの、現場では年齢によるハードルが存在します。
しかし、実際の採用データや企業の法定雇用率達成の動きからもわかるように、40代・50代・60代でも十分にチャンスがあります。
例えば、体力や健康状態を考慮した勤務形態、経験を活かせる業種、安定した勤怠のアピールなどは、どの年代でも有効な戦略です。
また、法定雇用率引き上げのタイミングや、企業の継続雇用制度、無期転換ルールなどの制度を活用することで、採用の可能性を高められます。
年齢を理由に諦める必要はありません。



情報収集と戦略的な行動を重ねれば、年齢や障害に配慮しながら長く安心して働ける職場と出会うことは十分可能です。
もしこれから求人を探すなら「書類の作成」「面接アドバイス」「求人紹介」してくれるエージェントサービスを活用しましょう!
以下のエージェントは完全無料で利用可能なので今のうちに登録しておきましょう!

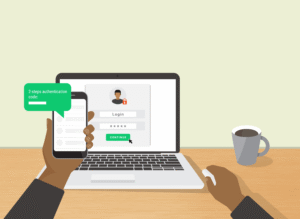







コメント