- 障害者雇用に応募しても不採用ばかり…。
- どうして自分だけ受からないんだろう?
そんな風に悩んでいませんか?
「落ちる人」には共通する理由があり、そこを理解できないと同じ失敗を繰り返しやすいんです。
でも安心してください。この記事はそんな悩みを解決します。
ここで紹介する「不採用を避ける12の秘訣」を実践すれば、面接や書類選考で落ちていた人でも“採用される人”に近づけます。
記事の前半では「障害者雇用不採用の理由」や「受からない人の特徴」を分かりやすく整理。
後半では「採用されるための具体的な対策」を10個紹介します。
 ウキタ
ウキタ不採用続きで悩んでいるあなたはぜひ最後までご覧ください。


- 名前:ウキタ
- 障害者雇用枠で7年勤務
- 3社で障害者雇用枠勤務
- atGPとdodaャレンジ利用経験
- 人事担当経験あり
障害者雇用の現状と採用の課題
障害者雇用の制度は整備が進んでいる一方で、現場には課題が残っています。
ここでは最新の統計や傾向をもとに、採用の現状を整理していきます。
障害者雇用の現状(雇用率・採用状況をデータで解説)
法定雇用率は2025年に2.7%へ引き上げられました。
| 2023年度 | 2024年4月度 | 2025年7月度 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
年々法定雇用率の枠は増え続けており、障害を抱える僕たちにとっては有利な状況が続いてます。
法定雇用率を満たしてる企業は46%なので枠に余裕があるんです。



つまり障害者雇用で働けるチャンスは十分になるってこと。
障害別 働く人数と年代
障害別で働いている人数と年代について解説します。
身体障害者の雇用傾向
身体障害者は50代以上の就業者が目立ちます。理由は、義務化が1976年と早く、長年の雇用実績が積み重なっているためです。例えば、全体の半数近くを中高年が占めています。
要するに、経験豊富な層が安定して働いているのが特徴です。
知的障害者の雇用傾向
知的障害者は20代の採用割合が高いです。
背景には、特別支援学校からの就職支援が強いことがあります。
具体的には、清掃・製造など現場で活躍する例が多いです。
そのため、若いうちから職場に定着しているケースが目立ちます。
精神障害者の雇用傾向
精神障害者は20代から40代にかけての就労が多いです。
なぜなら、2018年から雇用義務化され、求人が増えたからです。
例えば、令和6年の調査では精神障害者の就職件数は6万5千件を超えています。
繰り返しますが、支援制度の拡大が就業機会を後押ししています。
発達障害者の雇用傾向
発達障害者は20代〜30代の就労者が多くなっています。
理由は、雇用対象に加わったのが近年であり、若い世代の就職活動が主流だからです。
例えば、データ分析や事務作業など得意分野を活かした職種での採用が増えています。
つまり、適性に合った職場で力を発揮できるケースが増加中です。
法定雇用率と企業が採用しない理由
法定雇用率の達成率は2024年時点で46%にとどまっています。
根拠は厚労省の雇用状況集計結果です。
達成できない理由は、配置できる業務が少ない、支援体制が整っていないなどです。
つまり、制度上の義務と企業の現実との間にズレがあります。
精神障害・発達障害は本当に採用されにくいのか?
実際には就職件数が年々増加しています。
理由は、精神障害者福祉手帳の取得者増加や雇用義務化による求人増です。
例えば、精神障害者の就職件数は身体・知的障害者よりも多くなっています。
要するに、採用されにくいどころか、支援を活用すれば十分に可能性があります。
障害者雇用の不採用理由4選
障害者雇用の応募で不採用が続くと「自分のせいなのかな?」と落ち込みがちですが、実は共通するパターンがあります。ここでは、よくある4つの理由を整理して紹介しますね。
書類選考で不採用になる理由
書類で落ちる場合、多くは「伝わり方」の問題です。
なぜなら、履歴書や職務経歴書は応募者の第一印象を決める重要な材料だから。
- 記載内容に不備がある
- 記載内容があってない(例卒業月等)
- 志望動機がテキトーに書かれてる
上記に当てはまると採用担当者からはマイナスな印象を与えてしまいます。
企業が「業務にマッチする人材か」を判断できる情報が不足している状態なんです。



応募先ごとに職務内容を意識した書類を整えることが、
通過率アップには絶対条件ですよ!
面接で不採用になる理由
面接は「人柄」と「働く姿勢」を見られる場です。
というのも採用担当者が入社後の働き方をイメージしてるから。
具体的には、障害の説明が不十分で「何ができて何が難しいのか」が伝わらない場合、企業側は不安を感じやすくなります。
また、体調管理に不安があったり、志望動機がはっきりしないと「長期的に働けるのか」と疑問を持たれます。
質問に対して的を射ない回答をしてしまうと、コミュニケーション力が不足していると判断されることも。



面接では誠実さや素直さを意識し、自分の言葉で働く意欲を伝えることが欠かせません。
実習や試用期間で不採用になる理由
実習や試用期間では「実際に働く姿勢」が評価されます。
なぜなら、書類や面接では見えない部分を企業が確認する場だから。
例えば、時間を守れない、報告・連絡・相談が不足していると「職場適応が難しい」と判断されがちです。
また、体調管理ができず欠勤が続く場合も、安定した勤務が難しいとみなされます。
実際に、業務スキル不足よりも「協調性」や「基本的な勤務態度」が原因で不採用になることが多いのです。
完璧なスキルよりも「働く上での基本」を見られているということ。



実習や試用期間はスキルより姿勢を重視して臨むのが大切ですよ!
障害の内容で不採用になる理由
障害そのものが不採用に直結することもあります。
理由は、企業によって受け入れられる範囲や配慮体制が異なるからです。
例えば、専門的な支援が必要なのに職場に体制が整っていない場合、採用が難しいと判断されてしまいます。
実際に、配慮事項が多すぎたり内容が不明確だと「この職場では対応が難しい」と見なされることも。
能力や人柄以前に「働く環境との相性」が合わないケースです。
繰り返しますが、これは個人の努力不足ではなく、制度や受け入れ体制の問題によるもの。



大切なことは、環境に合う職場を探し、支援機関を通じてマッチング精度を高めていくことです。
不採用フラグに繋がる原因がわかるチェックリスト
面接や選考で落ち続けるときは、自分でも気づかないクセや態度が原因になっていることがあります。
なぜなら、採用担当者はスキルだけでなく「一緒に働ける人かどうか」を重視して見ているからです。
例えば、
- 挨拶できない
- 質問に関してずれた回答をする
- 志望動機があいまい
上記はマイナスな評価に繋がります。
つまり、内容そのものよりも「印象の悪さ」が不採用につながるケースは多いのです。
| No | 項目 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 1 | 質問に的外れな回答を繰り返す | ☐ |
| 2 | 会話が成り立たない | ☐ |
| 3 | 話が長すぎて要点が不明確 | ☐ |
| 4 | 内容に一貫性がなく矛盾が多い | ☐ |
| 5 | 嘘っぽい・胡散臭い話し方をする | ☐ |
| 6 | 質問に対して沈黙が多すぎる | ☐ |
| 7 | 聞かれていないことばかり話す | ☐ |
| 8 | 挨拶ができない、声が小さい | ☐ |
| 9 | 身だしなみがだらしない | ☐ |
| 10 | 態度が偉そう | ☐ |
| 11 | 面接中にスマホをいじる | ☐ |
| 12 | 面接官の話を遮る | ☐ |
| 13 | 視線を合わせない、落ち着きがない | ☐ |
| 14 | 笑顔が全くなく、覇気を感じない | ☐ |
| 15 | 企業研究をしていない | ☐ |
| 16 | 志望動機が曖昧で具体性がない | ☐ |
| 17 | 「どこでもいい」といった発言 | ☐ |
| 18 | 自分の強みやできることを説明できない | ☐ |
| 19 | 質問回答で「わからない」連発 | ☐ |
| 20 | 障害理解が浅い | ☐ |
| 21 | 就業意欲が感じられない | ☐ |
| 22 | 集団で働くことを拒否する態度 | ☐ |
| 23 | 指示に従う気がない発言をする | ☐ |
| 24 | 勤務条件に柔軟性がなく要求が多い | ☐ |
| 25 | 職場の文化・雰囲気に合わない | ☐ |
| 26 | 協調性がなく自分中心の発言が多い | ☐ |
| 27 | 過去の職場や人を悪く言う | ☐ |
| 28 | 仕事に必要な基礎能力が不足 | ☐ |
| 29 | 健康管理ができていない | ☐ |
| 30 | 長期的に働く意思が感じられない | ☐ |



このリストを一度やって当てはまるものを改善していくと、
落ちる原因が自然と減っていきますよ。
不採用通知を受け取ったときの対応3選
障害者雇用の就活では、不採用通知を受け取ることは誰にでもある経験です。
「落ちる人=能力がない」というわけではありません。
ここでは気持ちを立て直し、次の採用につなげるための考え方を3つ紹介します。
「何社も落ちるのは普通」と理解する
不採用通知が続くと「自分だけが受からないのでは」と思いがちですが、就活では何社も落ちるのが当たり前です。
なぜなら、企業の採用枠は限られており、全員が受かることはないから。
例えば、10社受けて1社に採用されるケースも珍しくありません。



不採用通知を受けても「普通のこと」と割り切ることが大切!
そのため、不採用通知を受けても「普通のこと」と割り切ることが大切。
「相性の問題」だったと考える
採用されないと「自分がダメだからだ」と思いやすいですが、実際は企業との相性の問題が大きいです。
根拠は、障害特性や必要な配慮が会社の業務に合うかどうかで判断されるから。
例えば、静かな環境で力を発揮できる人が、忙しい接客業に応募した場合はマッチしにくいでしょう。



不採用通知は「自分に合う職場探しのヒント」と前向きに考えよう!
気持ちを整理する時間を取る
不採用通知を受け取ると気持ちが沈み、「どうせ受からない」とネガティブになりがちです。
なぜなら、就職活動は精神的な負担が大きく、落ちる人ほど焦りが強まるから。



ちなみに僕は就活で50社落ち続けた際、
「もうどうにでもなれ!」と開き直った結果無事内定に繋がりました。
落ち込む時間と気持ちを切り替えることを意図的にすることが大事ですよ。
障害者雇用で受からないを避ける9の対策
不採用が続くと「もう採用されないのでは」と不安になりますよね?
ですが、就活の進め方を工夫することで通過率は大きく変わります。ここでは具体的な対策を紹介します。
障害者求人に特化したエージェント活用
障害者雇用の専門エージェントを利用すると、受からない状態を抜け出しやすくなります。
なぜなら、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの特性や希望条件に合った求人を紹介してくれるからです。
例えば【dodaチャレンジ】や【アットジーピー(atGP)】では、在宅勤務や時短勤務といった柔軟な求人も多く取り扱っています。



僕が就活の際50社以上落ち続け最後の砦として活用したのが、
atGPエージェントでした。
その結果無事10月ごろ滑り込みで内定をゲットすることができました。
- 面接の日程調整をしてくれる
- 企業についての情報提供
- あなたにあった求人紹介
- 履歴書や職務経歴書の添削
- 面接の練習
- 出社日の調整
上記を全て1人でやるのは大変ですすよね?これを全て無料でサポートしてくれるのでエージェントを使わない手はありません。
就労移行支援の活用
就労移行支援は、受からない人にとって強い味方です。
理由は就労に向けたサポートを最大2年間してくれます。
- 必要最低限のビジネスマナーを学べる
- 最低限のPCスキルを学べる
- 軽作業(封入、組み立てなど)の体験
- 自己理解・職業適性の把握できる検査
- 就職・転職活動の支援(面接や履歴書の書き方等)
また就労移行支援では定着支援を行ってる事業所もあります。
就職後に不安が出ても相談できる環境が整っています。



もしなかなか採用されない状況が続くなら、
一旦就労移行支援でスキルを習得するのも手です。
ハローワーク・専門相談員への相談
ハローワークは障害者専門の窓口を設けており、受からない悩みに合わせたサポートを受けられます。
なぜなら、相談員が障害特性や就業条件を理解した上で、応募できる求人を一緒に探してくれるからです。
具体的には「障害者トライアル雇用」や「職場実習制度」を通じて、実際の職場を体験できる制度もあります。
事前に数日間の実習を行い、職場との相性を確認してから応募に進むことでミスマッチを減らすことも可能に。



ハローワークとエージェントをうまく使い分けることで、
採用につながりやすくなりますよ!
履歴書・職務経歴書の改善
書類選考で受からない人は、履歴書や職務経歴書の書き方に課題で不採用になってる可能性大。
応募書類が企業にとって最初の判断材料になるから。
例えば、ブランク期間に関して何一つ記載がなければ「今までこの人は何してきたのか?」とマイナス評価に繋がります。
「就労移行支援に通いスキル習得」と書いてあれば前向きな印象になりますし、志望動機も「この職場で貢献できる具体的な理由」を入れることで採用担当者の目に留まりやすくなりますよね?



書き方を少し工夫するだけで「落ちる書類」から「選ばれる書類」に変わるのです
そのため、第三者の添削や支援機関のチェックを受けるのが効果的!
面接対策を行う
面接で受からない原因は、多くの場合「伝え方」にあります。
理由は、面接官はスキル以上に「一緒に働ける仲間かどうか」を重視しているからです。
例えば、質問に的確に答えられなかったり、障害の説明が曖昧だと不安要素と受け取られやすくなります。
もし緊張で言葉が出にくい場合でも、事前に模擬面接を繰り返しておけば、回答の流れを自然に伝える事が可能です。



「自分の強み・できること」と「必要な配慮」を整理して伝えられることが大切です。
なので、支援機関やエージェントを通じて練習し、自信を持って臨めるように準備することがカギです。
自己PR・障害説明の改善
自己PRや障害の説明がうまくできないと、採用されない大きな要因になります。
企業が「できる業務」と「必要な配慮」を理解しにくくなるからです。
例えば、「体調が安定していれば事務作業を正確に続けられる」「人と関わる業務は苦手だがPC入力は得意」といった具体的な表現が効果的です。
つまり、正直かつ前向きな伝え方をすれば「この人なら職場で活躍できる」と思ってもらいやすくなります。



自己理解を深め、整理してから臨むことが採用につながりますよ!
健康・メンタルのセルフケア
受からない状態が続くと、心身の調子が不安定になりやすいです。
採用側は「長く働けるかどうか」を大切に見るから。
例えば、体調不良で欠勤が多いと判断されると採用が難しくなります。
なので、
- しっかり睡眠リズムが整ってる
- 定期的に通院して主治医から指導を受けてる
- きちんと公私で気分転換ができている
といった基本的なセルフケアが重要です。



健康を維持すること自体が「働き続けられる力」の証明になりますよ!
得意な業務への応募に絞る
不採用が続く理由の一つに「仕事内容とのミスマッチ」があります。
自分の特性に合わない職種に応募してると、知らずのうちに不採用通知になるリスクが高まってるんです。
例えば、人と話すのが苦手なのに接客業ばかり受けていれば採用されにくいのは当然。
面接の話し方でばれますよ。
逆に、集中力を活かせるデータ入力や製造補助など、自分の得意分野に近い職種を狙えば通過率は上がります。



まずは己理解を深めて応募を絞り込むようにしましょう。
自己理解を深める
受からない状態を抜け出すには、まず自分を理解することが大切です。
理由は、強みや弱みを整理できれば、企業に対して明確に説明できるからです。
例えば、「集中力は高いが体力面には不安がある」「一人作業が得意で正確性に自信がある」といった自己分析は、応募先の仕事との相性を見極める材料になります。
つまり、適性を把握できれば「採用されない職種」に応募する無駄を減らせるんです。



支援機関やキャリアシートを活用しながら整理するのがおすすめです。
よくある質問Q&A
- 障害者雇用 面接 不採用 フラグになる理由はなぜ?
-
障害への配慮ばかりを強調しすぎて、「仕事をやる気があるのかな?」と思われてしまうと不採用につながりやすいです。企業は一緒に働く仲間としての前向きさも見ています。
その他の理由は以下の記事でまとめてます。あわせて読みたい
 障害者雇用面接の合格&合格フラグのサイン!通過率UPさせる1つの秘策を伝授 下記のことを知りたいあなたにおすすめ! 面接の合格フラグは参考にすべき? 合格フラグを知りたい! 落ちる人採用される人の差は何? 面接の通過率を上げる方法を教え...
障害者雇用面接の合格&合格フラグのサイン!通過率UPさせる1つの秘策を伝授 下記のことを知りたいあなたにおすすめ! 面接の合格フラグは参考にすべき? 合格フラグを知りたい! 落ちる人採用される人の差は何? 面接の通過率を上げる方法を教え... - 障害者雇用で書類選考が通らないのはなぜ?
-
自己PRや職務経歴で「働ける力」がうまく伝わっていないと、書類選考は通りにくいです。配慮事項だけでなく、できることも具体的に書くのが大切です。
まとめ障害者雇用は受からない理由を知れば改善可能!
障害者雇用で「なかなか採用されない」と悩むのは、多くの人が経験していることです。
落ちる理由は、
- 書類や面接での伝え方
- 体調や生活リズムの不安
- そして職場との相性
いくつかの共通点に整理できます。
つまり、不採用は必ずしも「自分の能力不足」だけが原因ではないのです。
実際に、エージェントや就労支援機関を活用して書類の改善や面接練習を重ねたり、自分の得意分野に絞って応募するだけで採用につながった事例は多くあります。
繰り返しますが、受からない経験は改善点を見直すきっかけになります。



大切なことは、落ち込みすぎず、支援を受けながら次の行動に繋げること。
理由を知って一つずつ対策すれば「働きたい職場に出会えるチャンス」は必ず広がります。
受からない状況からなかなか抜け出せないあなたへ
「不採用ばかりで自信がなくなった…」そんな気持ちを抱えていませんか?
エージェントを活用すれば、書類添削や面接練習も一緒に取り組めるので、一人で悩む必要はありません。
就職&転職のプロと相談する子できっと内定を勝ち取ることができるはず!



僕自身も就活時50社以上落ち続け「終わった」と思いました。
ただエージェントを活用した結果無事内定ゲットしたんです。
以下のエージェントは無料で利用できるので今のうちに登録しておきましょう!
▶ 就活の不安をプロと一緒に解消!
- ✅ アットジーピー【atGP】:スカウト機能付きで在籍しながら転職活動できる!
- ✅ dodaチャレンジ:専任アドバイザーによるキャリア提案が強み
- ✅【ランスタッド】(障害者支援):外資・大手企業の障害者求人に強い

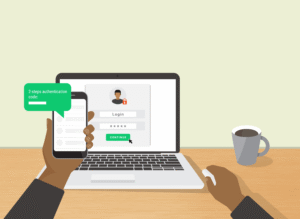







コメント