- 障害者雇用で大企業で働く人が増えてるの?
- 大手企業の取り組み事例って?
- 障害者雇用で大企業で働ける人の条件は?
- 大企業に働くための求人の探し方は?
「障害があっても、ちゃんと働ける大企業ってあるのかな…」「制度とか求人の探し方がわからなくて不安…」──そんなふうに感じていませんか?
この記事は、そんな悩みを解決します。
障害者雇用に積極的な“大企業の取り組み”や“安心して働ける職場の見つけ方”を知ることで、あなたに合った働きやすい会社に出会えるようになります!
実際に私も、制度や求人の探し方を理解したことで、自分にフィットする大手企業に転職できました。
記事の前半では「大企業が行っている障害者雇用の取り組み」を紹介し、後半では「具体的な求人の探し方や支援制度の活用法」を丁寧に解説します。
不安を自信に変えるヒントがきっと見つかるはずなので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

- 名前:ウキタ
- 障害者雇用枠で7年勤務
- 3社で障害者雇用枠勤務
- atGPとdodaャレンジ利用経験
- 人事担当経験あり
大企業で働く障害者が増えている5つの要因
近年、大企業で障害者雇用が進んでいる背景には、法制度だけでなく、働きやすさ・支援体制の充実といった要素があります。ここではその代表的な理由を4つ紹介します。
- 法定雇用率による採用枠の多さ
- 安定性・福利厚生・制度面での充実
- キャリア支援と多様な職域
- 高年収を狙えるチャンス
法定雇用率による採用枠の多さ
大企業は法律に基づいて、より多くの障害者を雇用する必要があります。
一定規模以上の企業には「法定雇用率」と呼ばれる基準が定められており、例えば従業員数が1000人を超える企業では、3%以上の障害者を雇用することが義務づけられています。
未達成の企業には、1人あたり月5万円の納付金が課されるため、企業側にとっても実務的・経済的なインセンティブがあるんです。
また、達成企業には助成金が支給される場合もあり、積極的な雇用につながっています。
 ウキタ
ウキタつまり、大企業には自然と障害者の採用枠が広がりやすい土壌があるのです。
安定性・福利厚生・制度面での充実
大企業が選ばれる理由のひとつは、働く上での「安心感」が違うからです。
健康保険や有給休暇、産業医の常駐など、基本的な福利厚生が充実しているだけでなく、障害者向けに配慮された制度も整備されている企業が多くあります。
- 定期的な面談制度
- ジョブコーチを利用できる
- 就業時間の柔軟対応
- 通院配慮
- 通院のための特別休暇
中小企業よりも大企業のほうが長期的に無理なく働ける環境が整っている可能性大。
また、従業員数が多いため、急な体調不良や業務調整にも柔軟に対応できるのが魅力ですね。



結果として、精神的にも安定して働ける職場になりやすいのが大企業です。


キャリア支援と多様な職域
大企業は部署や業種が多岐にわたるため、障害の特性やスキルに合わせて働ける職種の選択肢が豊富です。
たとえば、事務職や総務、人事といった定型業務はもちろん、IT部門でのシステム管理やデザイン、品質管理など、専門性を活かせる職種も用意されています。
また、社内研修やeラーニング制度が整っており、「働きながらスキルアップしたい」というニーズにも応えてくれます。



僕が2025年字に働いている会社ではAI研修等が行われます。
適性に合った仕事を見つけやすく、無理なく成長できるのが大企業の強みです。
将来的に異動や昇進のチャンスもあり、キャリア形成にも前向きになれます。
高年収を狙えるチャンス
障害者雇用でも、条件によっては年収アップを狙えるのが大企業の魅力です。
基本給や賞与が安定しており、正社員登用制度を活用すれば月給ベースで大きく変わるケースも少なくありません。
また、勤続年数や社内評価に応じて昇給・昇格・昇進の道も開かれており、長く働くことでしっかりと報われる環境があります。



「雇用の安定」と「生活の安定」を両立したい人には、大企業は非常に現実的な選択肢ですね!


実績のある大手企業の取り組み事例
実際に障害者雇用へ積極的に取り組んでいる大手企業では、環境整備から人材育成まで多面的な工夫がされています。ここでは代表的な6つの事例をご紹介します。
- 特別支援学校の見学
- 職場のバリアフリー化
- 特例子会社を活用した雇用モデル
- 実際に働く人の事例と声
- ユニバーサルマナー検定実施
特別支援学校の見学
一部の大企業では、障害者雇用の新たな人材確保や理解促進のために、採用担当者が特別支援学校を訪問する取り組みを行っています。
早い段階から生徒と交流することで、生徒自身も「社会で働く自分」を具体的にイメージできるようになります。
たとえば、企業説明会を校内で実施したり、職場体験の受け入れを行うことで、ミスマッチを防ぐことにもつながっています。
採用する側も、現場の教員や支援者と連携を深めることで、配慮の必要性や能力の見極めに役立つ情報を得られます。



こうした関係性の構築が、より良い障害者雇用の土台をつくっているのです。
職場のバリアフリー化
働く環境そのものが安全で快適であることは、障害のある方にとって非常に大切なポイント。
大企業では、エレベーターの点字案内、車いす対応のトイレや出入り口の自動ドア化、段差の解消など、物理的なバリアフリー化が進んでる場合が多いです。
また、聴覚障害のある方向けに光で知らせる装置を設置したり、会議での手話・文字支援を導入している企業も増えています。
これにより、障害の種別にかかわらず、従業員が安心して働ける職場が実現されています。



大企業では資金力があるためバリアフリー化に投資して、
人材確保を進めてるんです。
特例子会社を活用した雇用モデル
特例子会社は、障害者雇用に特化した企業グループ内の法人で、働きやすい環境や業務を整えた場として機能しています。
大企業の多くがこの制度を活用し、清掃・文書スキャン・IT入力作業など、障害の特性に合わせた職務を提供しています。
たとえば、あるIT系企業の特例子会社では、発達障害のあるスタッフがデータチェック業務に集中しやすいよう、静かな個別ブースを設置。
さらに、専門スタッフが常駐し、業務中の困りごとに即時対応できる体制を整えています。



こうした支援環境があることで、就労の継続率も高く、本人の自信や成長にもつながってるんです。
実際に働く人の事例と声
「最初は不安だったけど、今は楽しく働けています」と語るのは、ある大手製造業に勤務する聴覚障害者の方。
入社当初は筆談やチャットを活用しながら同僚とやり取りを重ね、徐々に信頼関係を築いてきました。
また、別の企業では発達障害のある社員が社内のITサポート部門で活躍しており、細かなマニュアル作成が得意という強みを生かして評価されています。
こうした実例は、「自分にもできるかも」と思える希望を与えてくれます。



経験談を社内報やホームページで公開している企業もあり、透明性の高さが応募者の安心感にもつながっていますね。
ユニバーサルマナー検定実施
最近では、障害のある社員を受け入れるだけでなく、「共に働く社員」の理解を深める取り組みも重視されています。そのひとつが、ユニバーサルマナー検定の導入です。
たとえば、受付・人事・管理職といったポジションに就く社員に取得を推奨し、言葉選びや対応姿勢を整えることに役立てています。



こうした教育を行うことで、職場全体が「お互いに気を配り合える空気」に変わっていくのです。
ユニバーサルマナー検定の詳細
障害者雇用の実態について
障害者雇用と一口に言っても、業界や雇用形態、雇用元によって待遇やキャリアの差があります。
ここでは、現実的な年収や雇用形態ごとの違いを具体的に見ていきましょう。
- 障害者雇用で高年収が狙える業界
- 正社員・契約社員の待遇差
- 特例子会社と本体雇用の収入と昇進の違い
障害者雇用で高年収が狙える業界
障害者雇用でも、業界によっては高年収を目指せます。
特にIT業界や製造業、金融業では専門職が多く、スキル次第で年収400万〜500万円台に届くケースもあります。
たとえば、IT系ではシステム管理やエンジニア補助、金融系ではデータ集計やリスク分析などの職種で活躍する方も少なくありません。
これらの業界は人材育成に力を入れており、成果に応じた評価制度も導入されています。
一般的に「障害者雇用は給料が低い」と言われがちですが、適性やスキルを活かせる職場を選べば、収入面でも十分に満足できるはずです。
正社員・契約社員の待遇差
| 待遇項目 | 正社員の一般的な扱い | 契約社員の一般的な扱い |
|---|---|---|
| 雇用期間の安定性 | 無期雇用で定年まで継続可能 | 有期契約で更新やクビの可能性 |
| 給与水準(基本給) | 高めで昇給機会がある | 低めで昇給機会が少ない |
| 賞与・ボーナス | 年2回など安定的に支給される | 支給されないか少額・不定期 |
| 退職金制度 | 勤続年数に応じて支給される | 対象外か支給額が小さい |
| 昇進・昇格機会 | 管理職や責任あるポストに昇進可能 | 昇進機会が少ない |
| 福利厚生・手当 | 住宅・家族・通勤手当などが充実 | 手当が限定的で対象外も多い |
| 社会保険加入 | 条件を満たせば加入でき将来保障厚 | 勤務条件次第で未加入の場合もある |
| キャリア形成・研修 | 研修制度やキャリアパスが整備 | 研修が少なくキャリア形成が難しい |
| 異動・転勤・勤務地 | 異動や転勤があり経験を積める | 異動や転勤がほぼなく勤務地固定 |
| 解雇・雇止め | 解雇は正当理由が必要で安定 | 契約満了で終了する可能性 |
同じ企業で働いていても、正社員と契約社員とでは待遇に大きな差があります。
正社員は基本給の安定に加え、賞与や退職金、昇進のチャンスなどが与えられやすい一方で、契約社員は時給制や有期雇用であることが多く、年収も低くなりがちです。
とくに障害者雇用枠では、最初は契約社員からスタートするケースが多く、正社員登用制度の有無が長期的な働き方に大きく影響します。



待遇の差は、将来の生活設計にも関わってくるため、慎重な判断が求められます。
特例子会社と本体雇用の収入と昇進の違い
特例子会社と本体雇用とでは、収入や昇進のチャンスに違いがあります。
特例子会社は障害者が働きやすいように配慮された環境ですが、職務内容が限定的で、賃金水準はやや低めに設定されていることが多いです。
一方で、本体雇用では他の社員と同等の評価制度が適用されることもあり、昇進や給与面での上積みが期待できます。ただし、その分、業務内容や責任も重くなるため、無理のない範囲で挑戦できるかがカギになります。



どちらが良いかは一概に言えませんが、「働きやすさ」か「待遇」か、何を重視するかで選び方は変わってきます。
障害者雇用で大企業で働ける人の条件
「どうすれば大企業で障害者雇用に採用されるの?」という疑問は多くの方が抱くもの。
ここでは、実際に働いている人たちの共通点や選考で評価されたポイントをご紹介します。
- 社会人基礎力がある
- 成長意欲がある
- 長期的に働く意思や実績
- ITや英語、専門知識
- 簡単なパソコン操作ができる
社会人基礎力がある
社会人基礎力とは、経済産業省が2006年に提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」で、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力(計12要素)から構成されています。
経済産業省社会人基礎力
なぜこの力が重視されるかというと、人生100年時代や技術革新が進む現代では、変化に対応し続ける柔軟性と自律性が求められるからです。
例えば、指示を待つだけでなく自ら課題を見つけ挑戦する「前に踏み出す力」、問題の本質を捉えて思考する「考え抜く力」、異なる意見を尊重しながらチームで協働する「チームで働く力」、こうしたバランスが取れている人は、周囲から信頼され成果を出しやすくなります。



社会人基礎力がある人とは、自分のキャリアを主体的に築きながら、周囲と協調しつつ継続的に学び行動できる人です。
成長意欲がある
スキルや経験が少なくても、「これから学びたい」という前向きな姿勢は企業に好印象を与えます。
たとえば、業務に関連する資格取得を目指していたり、就労移行支援でビジネスマナーを学んでいることなどは評価ポイントです。
特に大企業では、入社後も研修や教育体制が整っていることが多く、「伸びしろがある人材」を求めている傾向があります。



「完璧にできる」よりも、「できるようになろうとしている」姿勢が大切です。
過去ではなく未来への意欲が、採用を左右するケースも少なくありません。
長期的に働く意思や実績
企業は採用するからには、できるだけ長く働いてくれる人を望んでいます。
障害者雇用でも同様で、「安定して勤務できそうか」は選考で必ず見られるポイントです。
たとえば、アルバイトや就労移行支援で週20時間以上の勤務を半年以上継続した経験があると、実績として高く評価される傾向にあります。
また、「将来的にもこの会社で成長したい」といった継続意思を明確に伝えることで、より信頼感を得やすくなります。
短期離職の経験がある場合でも、今後の意欲をしっかり言語化できれば前向きに評価されることもあります。



長期的に働けるという客観的な証拠を伝える事ができればOK!
ITや英語、専門知識
スキルがあると、それだけで活躍の場が広がります。
特にITスキル(Word、Excel、データ入力など)や、英語、会計、法律、デザインなどの専門知識を持っている人は、一般枠の仕事と変わらないレベルで求められることもあります。
企業にとっては、障害の有無に関係なく「業務を任せられる戦力」として見られるため、選考でも高評価につながります。
もちろん、すでに持っている必要はなく、「スキルを身につけたい」という姿勢も評価対象になることがあります。



自分にとって興味のある分野から少しずつ学んでみるのもおすすめです。
簡単なパソコン操作ができる
今やどんな業種でも、ある程度のパソコン操作は求められる時代です。
- WordやExcelの入力
- メールの送受信
- Windowsの使い方
- 最低限のショートカットキー操作
業務上のマニュアルはある企業はふ増えてます。
ただパソコンの基礎スキルは「当たり前」が前提なので独学で進めていく必要あり。
「パソコンに自信がない…」という方も、就労支援などで少しずつ練習しておくと安心です。



まずはタイピングやExcelの入力練習から始めてみましょう。
自分に合った企業選び|障害別おすすめポイント
障害の特性によって、向いている働き方や職場環境は大きく異なります。
ここでは、発達・精神・身体のそれぞれに適した企業や配慮の例を紹介します。
- 発達障害に向いている働き方と企業環境
- 精神障害のある方に配慮ある制度・文化
- 身体障害者の就労支援とバリアフリー環境
発達障害に向いている働き方と企業環境
発達障害がある方には、作業が明確に区切られ、予測しやすい仕事環境が適しています。
たとえば、マニュアル化された業務や、ルーティンワークの多い仕事は安心感につながりやすいです。
最近では、大手IT企業が感覚過敏やコミュニケーションの困難さを配慮し、仕切りのある作業スペースやチャットツールでの連絡を導入しています。



環境への適応が難しいと感じる場合は、特例子会社など個別配慮の手厚い職場から始めるのも良い選択ですね。
精神障害のある方に配慮ある制度・文化
精神障害のある方にとっては、無理のない業務量と精神的な安定が得られる職場が重要です。
特に、こまめな面談や相談機会を設けてくれる企業や、休憩時間・勤務時間の調整が可能な環境は働きやすさにつながります。
たとえば、うつ病や不安障害のある社員に対し、通院日や「調子が悪い日」の自己申告制度を導入している企業もあります。
また、上司や同僚の理解が得られる職場文化があると、自己開示もしやすくなり安心して働けます。



見た目ではわかりづらい症状だからこそ、対話の機会と配慮の制度が整っているかが企業選びの鍵です。
身体障害者の就労支援とバリアフリー環境
身体障害がある方には、物理的な設備の整備とともに、移動・作業時のサポート体制がある職場が適しています。
たとえば、車いす利用の方には段差のないフロアや自動ドア、音声や点字の案内システムが整ったオフィスが望ましいです。
大企業では、こうしたバリアフリー設計が進んでおり、特例子会社ではさらに設備が充実しているケースもあります。また、通勤負担を軽減するために送迎制度や在宅勤務制度を導入している企業も。



配慮されている設備や制度は、企業ホームページや会社説明会で事前に確認しておくのが安心です。
障害者雇用種目別ランキング
「どんな企業や業種が障害者雇用に力を入れているのか?」を知ることは、自分に合った職場選びのヒントになります。
ここでは法定雇用率が高い企業・人気職種・業種別の傾向をご紹介します。
- 法定雇用率の高い企業
- 人気職種
- 法定雇用率が高い業種
法定雇用率の高い企業
障害者雇用率の高い企業として毎年注目されているのが、「ゼネラルパートナーズ」「ファーストリテイリング(ユニクロ)」「しまむら」などです。
たとえば、ゼネラルパートナーズは雇用率8.7%と法定の3倍以上を達成しており、自社で就労支援や転職サービスも展開しています。
また、ユニクロを展開するファーストリテイリングでは「1店舗1人の障害者雇用」を掲げ、全国的に雇用の裾野を広げています。
こうした企業は、単に雇うだけでなく、支援制度や研修体制も充実しており、安心して働ける環境が整っている点が評価されています。
人気職種
障害者雇用で人気が高い職種には、事務系・IT系・軽作業などがあります。
特に「一般事務」は、定型業務が中心でマニュアル化されているため、安定して働きたい人に人気です。
また、Excel入力やデータ処理などの「パソコン業務」も、リモートワーク対応が進んでいることから注目されています。
さらに、特例子会社などでは清掃・封入・軽作業など身体的負担が少ない仕事が用意されていることも多く、幅広い障害特性に対応しています。



スキルや得意なことに応じて、適職を選べる環境が整いつつあるのが現在の特徴です。
法定雇用率が高い業種
業種別で見た場合、障害者雇用率が高いのは「鉄鋼」「パルプ・紙」「小売業」「銀行業」「医薬品」などが上位に入ります。
たとえば、小売業は全国に店舗を展開している企業が多く、地域ごとに障害者雇用を推進しやすい構造を持っています。
銀行業や医薬品業界では、事務処理・データ入力といった職種が充実しており、オフィス内での就労が中心になるため、身体に負担の少ない働き方が可能です。



こうした業種は比較的法定雇用率を安定して達成しており、働く環境や制度も整っている傾向があります。
障害者雇用枠?特例子会社?で悩んでる方向けのチェックリスト
障害者雇用で働くといっても、「一般企業の障害者枠」と「特例子会社」では職場環境や仕事内容、求められることが大きく異なります。
たとえば、一般企業では健常者と一緒に働くケースが多く、業務遂行力や自立性が求められる一方で、キャリアアップのチャンスもあります。
一方、特例子会社は障害に配慮された環境で支援スタッフが常駐し、軽作業や補助業務を中心に、安定した就労がしやすいのが特徴です。



「挑戦したいか」「安心を優先したいか」など、自分の価値観や体調、希望に合った働き方を選ぶことが大切!
| 項目 | 障害者雇用枠(一般企業) | 特例子会社 |
|---|---|---|
| 1. 職場環境 | 健常者と一緒に働く | 障害者中心の環境 |
| 2. 求められる力 | 自立性・業務遂行力重視 | サポートを前提とした働き方 |
| 3. 業務内容 | 専門職や事務職が多い | 軽作業や補助業務が多い |
| 4. スキル成長 | キャリアアップの機会あり | 成長より安定が重視 |
| 5. 支援体制 | 配慮はあるが限定的 | 支援スタッフが常駐 |
| 6. 働きやすさ | 職場によりばらつきがある | 配慮された職場で安心 |
| 7. 給与水準 | 一般社員と同等が多い | 最低賃金に近いことが多い |
| 8. 人間関係 | 健常者との関わりが中心 | 障害者同士で安心感がある |
| 9. 働く目的 | 成長や挑戦を重視 | 安定した就労を重視 |
| 10. 向いている人 | 自立志向・挑戦したい人 | 支援が必要・安定志向の |
こんな人におすすめ
- 障害者雇用枠(一般企業)が向いている人:
→ 働きながらスキルアップしたい、自立志向がある、健常者と一緒に働くことに抵抗がない - 特例子会社が向いている人:
→ まずは安心して働きたい、障害への配慮が手厚い環境が必要、生活リズムを安定させたい
大企業就職に成功してる人が実践する求人の探し方3選
「どうやって大企業の障害者求人を見つけたらいいの?」と悩んでいる方は多いはず。
ここでは、実際に内定を獲得した人たちが活用している3つの方法をご紹介します。
- エージェントを使う
- 就労移行支援を活用
- ハローワークの活用
エージェントを使う
障害者専門の転職エージェントは、大企業の非公開求人や、自分に合った職場を効率よく探すのに役立ちます。
たとえば「atGP」や「dodaチャレンジ」では、希望や特性をもとに求人を紹介してくれるうえ、書類作成や面接練習まで手厚くサポートしてくれます。
中には、企業に対して条件交渉や「この人に合っています」と推薦までしてくれるエージェントもあります。
特に初めての転職や、働くことに不安がある方にとって、頼れるパートナーになってくれるはずです。
就労移行支援を活用
就労移行支援事業所は、就職に必要なスキルや知識を学べる“学校のような場所”です。
ビジネスマナーやパソコンスキルを身につけながら、実習や面接練習も受けられるのが特徴。
中には企業とのコネクションを持っていて、求人を紹介してくれるところもあります。
さらに、合同説明会や見学の同行など、就職活動全体を支えてくれるケースも。



生活リズムを整えながら少しずつ準備したい人には、とても相性がいい支援手段です。
ハローワークの活用
ハローワークは全国に拠点があり、無料で求人検索や就職相談が受けられます。
障害者専用の相談窓口がある施設も多く、履歴書の添削や模擬面接など、実践的なサポートが受けられるのが強みです。
また、「空求人(実際は採用していないもの)」が混ざっていることもあるので注意が必要です。
あくまで“補助的な手段”として活用するとよいでしょう。
よくある質問と不安の解消Q&A
- 障害者雇用=採用されやすいって本当?
-
障害者雇用は採用枠が法律で定められているため、一定数の募集が常にありますが「誰でも受かる」わけではありません。
企業は法定雇用率の達成だけでなく、業務を任せられるか、職場になじめるかも重視しています。
支援機関やエージェントを活用して、自分に合った企業選びや面接対策を行うことが、採用につながる鍵です。
あわせて読みたい
 障害者雇用で採用されやすい人とは?元人事が教える就職成功の秘訣! 下記のことを知りたいあなたにおすすめ! 障害者雇用の採用率はどのくらいなの? 障害者雇用の採用基準とは? 採用されやすい人の特徴って? 採用されるまでの流れを知...
障害者雇用で採用されやすい人とは?元人事が教える就職成功の秘訣! 下記のことを知りたいあなたにおすすめ! 障害者雇用の採用率はどのくらいなの? 障害者雇用の採用基準とは? 採用されやすい人の特徴って? 採用されるまでの流れを知... - 面接で障害をどう伝えるべきか?
-
面接では、障害の内容をすべて詳細に話す必要はありません。
大切なのは「どんな配慮があれば働けるか」を具体的に伝えることです。
たとえば、「週に1回通院がある」「静かな環境だと集中しやすい」など、業務に関係する部分に絞るのがポイント。



自分が働く上での工夫や、過去の成功経験を添えると、前向きな印象になります。
- 実際障害者雇用枠のリアルな評判が気になります。
-
匿名掲示板2chなどで実際に障害者雇用枠で働く方の体験談等があるので、参考にしてみるのもおすすめ。
ただ匿名なので参考程度にしておきましょう!以下の動画も2chのスレッド内奥をまとめて解説された動画です。
まとめ障害者雇用でも理想の職場で働ける!
障害があっても、大企業で安定して働けるチャンスはしっかりあります。
大切なのは、「自分にとって何が働きやすいか」を見極めること。
たとえば、キャリアアップを目指したいなら一般企業の障害者枠、無理なく働きたいなら特例子会社といったように、方向性をはっきりさせるだけでも選択肢が絞れます。
そして、求人探しではエージェントや就労移行支援を上手に使うことで、サポートを受けながら不安を減らして前に進めます。
この記事で紹介した内容をヒントに、自分らしく働ける職場をぜひ見つけてくださいね。
障害者雇用で大企業就職を目指したいあなたへメッセージ
「いつかは大企業で堂々と働きたい」
「家族やまわりに“すごいね”って言われるような仕事がしたい」
そんな想い、あなたの中にもきっとあるはずです。
でも、大企業の障害者枠ってどう探すの?どんな職場が自分に合ってるの?
そんな不安があるなら、今こそプロの力を借りてみてください。
「大企業なんて自分には無理かも…」と思っていた人も、チャンスを掴んでいます。
あなたもその一歩、踏み出してみませんか?


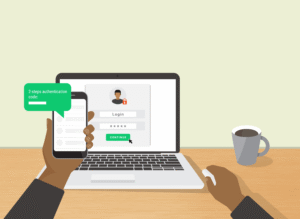






コメント